今回は助動詞を取り上げます。
前回の内容(英語の完了形とは?3つの形を例文でやさしく解説 | 1から学ぶ英語)をまだ見てない方は、こちらから先にご覧ください。
助動詞って色々意味があってややこしいですよね…。一気にやるとごちゃごちゃすると思うので、一つずつ整理していきましょう。
①can / could
まず初めにcanとcouldについて、この2つの単語は使い方は大体同じ。今後別の単元で取り上げますが、時制の一致を受ける際にcanが過去形のcouldとなります。
canもcouldもいくつか使い方があるので紹介していきます。
a)能力・可能
・He can speak three languages.
・We can see Mt. Fuji [from here].
・[When I was a child,] I could run [very fast].(子供の頃速く走れた)
・[When she was young,] she could run 10 kilometers [easily].(彼女は若い頃、楽に10km走れた)
上記の4つの例文は現在と過去で分けていますが、中学英語でもやってきたような意味としてとらえて大丈夫です。
ここで応用となりますが、hearやseeなどといった知覚動詞の前に置くと、「聞こえる」や「見える」のような受け身的な感覚を表す動詞を、進行形的に使う場合があり。
・I hear footsteps [in the hallway].(廊下で足音が聞こえる)
・I can hear footsteps [in the hallway].(廊下で足音が聞こえている)
b)可能性「~することがあり得る」
訳としては「あり得る」やcouldであれば「(ひょっとしたら)可能性がある」、反語的な言い方で「あり得るのだろうか。いや、そんなことがある訳がない」といった意味になるが、否定文では「あるはずがない」といった強い意味になります。
・Anyone can make mistakes.(誰でも間違えることはある)
・Smoking can cause serious health problems.
(喫煙は深刻な健康問題を引き起こす可能性がある)
・How can she know the answer?
(どうして彼女が答えを知っているというのだろう → いや、知っているはずがない)
・It could rain this afternoon.
(今日の午後、雨が降るかもしれない)
・How could you say such a thing?
(どうしてそんなことが言えるんだ、いや言えるはずがない)
・It’s so hot [today]. It couldn’t be snowy [tonight].
(今日はとても暑い、今夜雪が降るはずがない)
可能性や反語的な意味の例文を取り上げましたが、この用法はこのような使い方があります。可能性という意味ではcanとcouldで何が違うんやって感じですけど、テスト等に出る訳ではありませんが参考までに以下のような認識で良いかと思います。
| 用法 | can | could |
| 肯定的可能性 | 一般的・よくあること | 控えめ・不確実性あり |
| 反語的/否定 | 強い否定(〜のはずがない) | 控えめ・推測的否定(〜できるはずがない) |
※be able toV原形について
can・could共に能力・可能の意味の場合、未来や完了を表したい場合はbe able toV原形を使うが、一般的にはcanの方が普通のようです。以下で使い方だけ確認。
・I will be able to finish the report [by tomorrow].
(明日までにそのレポートを終えることができるだろう)
・We haven’t been able to find a good restaurant.
(私たちはずっといいレストランを見つけられないでいる)
参考までに、canとbe able toの違いとして、canは「身に備わった能力」、be able toは「一時的な能力・可能」を表す。
・She could solve complex problems [without any help].
(彼女は複雑な問題を一人で解くことができた)
・The rain stopped [briefly], so we were able to continue our walk.
(雨が一瞬止んだので、私たちは散歩を続けることができた)
※cannot be~で「~のはずがない」、cannot have 過去分詞で「~したはずがない」の意味を表す。
・He can’t be late.
(彼が遅刻するはずがない)
・They can’t have known [about the surprise party].
(彼らがサプライズパーティーのことを知っていたはずがない)
c)許可「~してもよい」
canが許可を表す場合は、次に説明するmayよりも口語的。否定語のcan’tは不許可(=禁止)を表す際、may not[mustn’t]よりも口語的。
・You can ask questions anytime.(いつでも質問していいよ)
・You can’t enter this room.(この部屋に入ってはいけません)
・Can I help you?(お手伝いしましょうか?)⇒申し出
・Can you pass me the salt?(塩を取ってもらえますか?)⇒依頼
他にcanを使った慣用句(cannot help~ing, cannot help but~等)もありますが、たいていの単語帳に載ってるのでそちらで覚えておけばいいでしょう。
②may / might
続いてmayとmightについてですが、ここは大きく分けると許可と推量となります。
ただ、mightに関してはほぼ推量で使われることがほとんどです。
a)許可「~してもよい」
・Students may use calculators [during the exam].(生徒は試験中、電卓を使ってよい)
・May I try this on?(これを試着してもよろしいですか?)
2つ目の疑問文について、許可する場合はOf course.やSure, go ahead.、Yes, you may.など。不許可の場合はNo,you may not. もしくは No, you can’t.となります。
※mayの過去形mightが過去の許可を表すのは、時制の一致以外では認められないので現在形では普通mayを使う。
・He said that I might go home early.(彼は私が早く帰ってもいいと言った)
saidを見て分かるように、文全体の時制は過去を表しているため時制の一致を受けてthat節の中ではmayの過去形mightが使われ、してもよいという意味になります。※文法用語で節は文(SとVが入ったかたまり)を表し、句はSとVが入っていないかたまり(前置詞+名詞等の修飾語句)を表します。
この他にも許可を求める表現もありますが、ここでは紹介のみにしておきます。
・Might I ask you a question?(質問してもよろしいでしょうか?)
⇒「非常に丁寧な依頼」を表す。これに関連して
I wonder if I might have….のような言い方もあり。
b)推量「~かもしれない」
推量の用法に関しては、大体50%のイメージを持っておけばいいかと思います。また、mightについては現在または未来のことについての推量を表しています。
・It may rain tomorrow.
・He may or may not come [to the party].
(彼はパーティーに来るかもしれないし、来ないかもしれない)
・Drinking too much coffee may weaken your bones.
(コーヒーを飲みすぎると骨をもろくするかもしれない)
・The shop might be closed today.
・He might feel nervous [before the interview].(彼は面接前に緊張しているかもしれない)
※might have 過去分詞は「~したかもしれない」という過去の事の推量を表す。
・They might have taken the wrong train.(彼らは間違った電車に乗ったかもしれない)
c)祈願
mayの用法となりますが、以下の使い方があります。
・May you be happy.(あなたが幸せでありますように)
・May you have a wonderful day.(素敵な一日になりますように)
・May your business prosper.(御社の事業が繁栄しますように)
may・mightに関しての基本的な用法は以上です。
また、mayやmightに関しては、「may[might]as well~」や「may[might] as well A as B」といった慣用表現もありますが、大抵の単語帳に記載があると思うのでここでの紹介は割愛します。
③must / have to
続いてはmustとhave toについて。基本的な意味は中学英語でも出てきていますが、高校英語でも出てくるような使い方もあるので以下で紹介していきます。
a)義務・必要
・You must[≒have to] wear a helmet when riding a bike.(自転車に乗るときはヘルメットをかぶらなければならない)
・Students must[≒have to] submit their homework [by Friday].(学生は金曜日までに宿題を提出しなければならない)
・They had to leave early [because of the traffic].(渋滞のせいで早く出なければならなかった)
・You must finish your homework, or you will fail the class.(宿題を終わらせなさい、さもないと単位を落とす)
中学英語でも出てきた使い方で、大体have toと意味は一緒になります。1つ目の文のように主語がYouの場合は命令文で書いても問題ないでしょう。勿論、主語が3人称単数で文が現在形の場合はhaveがhasになります。また、mustには過去形がないので、過去の事を言う時はhad toを使用。
・You don’t have to finish all the work today.
(今日すべての仕事を終わらせる必要はありません)
⇒念のため復習ですが、have toの場合否定文は「してはいけません」ではなく、「する必要がない」となります。疑問文でも同じようにdoを使用。
・Do I have to do homework now?
b)禁止
・You mustn’t smoke [in this building].
→主語がyouとなっている場合はDon’tで書き換え可能。have toにはこの用法はなし。
c)推量「きっと~だろう、きっと~のはずだ」
1)主に状態動詞と用いて、「きっと~だろう、きっと~のはずだ」の意味を表す。この場合be動詞が多く使われる。
・That must be the right answer.(あれが正しい答えに違いない)
⇒この意味での否定「~のはずがないだろう」はcannotとなる。
・That cannot be the right answer.(あれが正しい答えのはずがない)
2)must have 過去分詞「きっと~だろう」
・He must have missed the train.(彼は電車に乗り遅れたに違いない)
⇒否定の「~だったはずがないだろう」については、上記と同じくcannot[can’t]と使ってcan’t have 過去分詞で表します。
・He can’t have finished all that work in one day.(彼があの仕事を1日で終えたはずがない)
④shall
shallはアメリカではあまり使われなくなっており、イギリスでもくだけた言い方では次第に使われなくなってるそう。未来時制では1人称で使われるのも、最近では方言い方になっているそうです。
a)話し手の意思
主語が1人称の場合
・We shall overcome these difficulties.
(私たちはこの困難を克服するでしょう)
ポイント:
現代英語では I will ~ の方が一般的ですが、文章やフォーマルな場では I shall ~ が使われます
1人称で 単純な未来の予測 よりも 自分の意思・決意・提案 を強調したいときに使う
b)相手の意思
1)申し出・提案
・Shall I carry your bag?
(バッグを持ちましょうか?)
・Shall we go out for dinner tonight?
(今晩、夕食に出かけませんか?)
ポイント:
・主語がIの時は「私が~しましょうか?」という話し手の意思・申し出
→丁寧な表現で、相手の承諾を期待する
・主語がweの時は「一緒に~しましょうか?」という提案
→カジュアルでもフォーマルでも使える
⇒この意味では、先生によっては「~しましゃるか」で覚えさせる人もいるようです。
c)命令・禁止
・No one shall enter without permission.
(許可なしで入ってはいけません。)
💡 ポイント:
・1人称での意思・提案 → 現代でも普通に使う
・2人称・三人称での義務・禁止 → 聖書などで使われる他、契約書などで使われる。
・会話では will / must / can’t などで代替されることが多い
他にも助動詞はたくさんありますが、かなりの分量になるので一旦ここで終了とします。
今回はここまで。
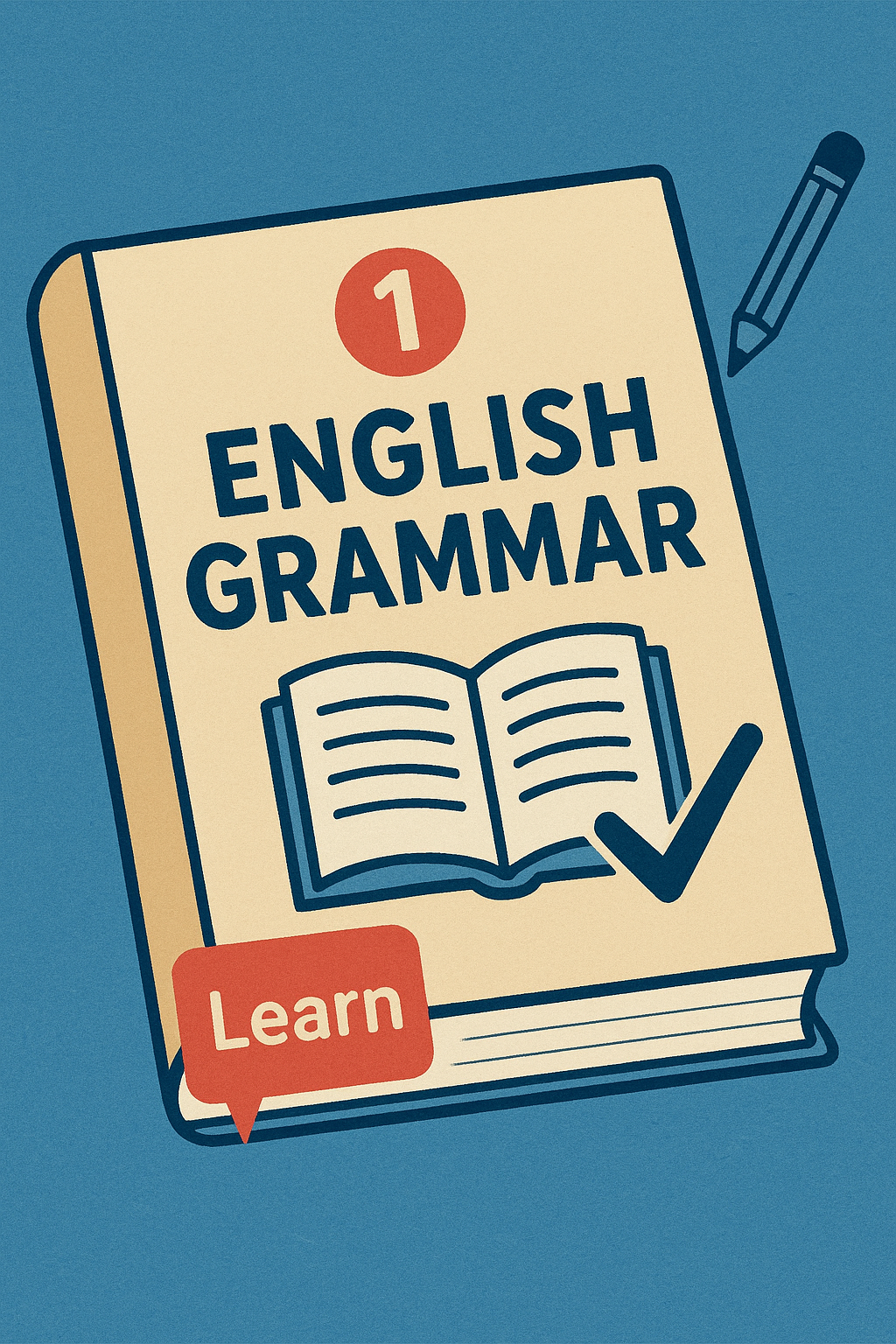
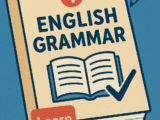
コメント